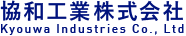採用担当者必見!有効求人倍率の見方と実践的な活用法
はじめに:なぜ「有効求人倍率」を知ることが大切なのか
「求人を出しても応募が来ない」
「思うような人材が採用できない」
こうした悩みを抱える中小企業は多くあります。その背景にある大きな要因のひとつが 労働市場の需給バランス です。
そしてこのバランスを示す重要な指標となるのが 有効求人倍率 です。
有効求人倍率は厚生労働省が毎月発表するデータで、「労働市場における人手不足・余剰の状況」を客観的に把握できる重要な数値です。本記事では、有効求人倍率の意味や見方、中小企業の採用戦略にどう役立つのかを、体験談や具体例を交えながら解説していきます。
有効求人倍率とは?
まず、釈迦に説法かとは思いますが改めて有効求人倍率がどのようなものか整理しておきましょう。
定義と計算方法
有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)に登録された「有効求人数」を「有効求職者数」で割った数値です。
有効求人数÷有効求職者数=「有効求人倍率」
- 1.0倍 → 求人と求職者が同数
- 1.0倍以上 → 求人が多く、人手不足
- 1.0倍未満 → 求職者が多く、売り手市場
例:
- 有効求人数:200件
- 有効求職者数:100人
- 有効求人倍率 = 200 ÷ 100 = 2.0
この場合、1人あたり2件の求人がある状態=企業側にとって人材獲得競争が激しい状況といえます。
有効求人倍率の推移と社会的背景
次に有効求人倍率の推移と社会的背景について触れていきます。
長戦後から高度経済成長期(1950〜70年代前半)
- 背景:戦後復興とともに産業が急速に拡大し、自動車・電機・鉄鋼など製造業が大量の労働力を必要としました。
- 有効求人倍率:常に1.0倍を超え、人手不足が当たり前の状態。
- 要因:
- 農村から都市部への人口流入(出稼ぎ労働)
- 「終身雇用・年功序列」といった雇用慣行の定着
- 大規模工場・インフラ投資による雇用の拡大
→ この時期は「企業が人材を選ぶ」より「企業が人材を奪い合う」時代でした。
バブル崩壊後(1990年代)
- 背景:バブル経済の崩壊による景気後退、不良債権問題で企業が採用を抑制。
- 有効求人倍率:1990年の1.4倍から急落し、1994年には0.6倍台まで低下。
- 要因:
- 大量リストラと新卒採用の「氷河期」突入
- 正社員採用の抑制と非正規雇用の拡大
- 企業が「即戦力」人材を重視し、新卒一括採用の縮小
→ ここから「売り手市場から買い手市場へ」の大転換が始まりました。
リーマンショック(2008〜2010年)
- 背景:世界的な金融危機で輸出産業が直撃。製造業の派遣切りが社会問題に。
- 有効求人倍率:2009年には0.42倍と、戦後最低レベルを記録。
- 要因:
- 輸出依存型の日本経済への打撃
- 雇用調整助成金などの制度で失業率は抑えられたが、新規求人は大幅に減少
- 若年層の雇用環境が悪化し、再び「就職氷河期」と呼ばれる状況に
コロナ禍(2020〜2022年
- 背景:外出自粛や観光・飲食業の需要蒸発。非正規雇用を中心に打撃。
- 有効求人倍率:2020年に1.0を割り込み、0.9倍台に。
- 要因:
- 飲食・宿泊・観光業で求人が激減
- IT・物流・医療など一部業種では人材需要が急増
- リモートワークの普及により「働き方の分岐点」となる
2023年以降の回復傾向
少子高齢化の影響で「構造的な人手不足」が鮮明化
背景:経済活動の再開とインフラ需要の拡大。
有効求人倍率:全国平均で1.3倍前後に回復(2023〜2024年)。
特徴:
製造業・建設業・運輸業など「現場系」の求人が多い
都市部はITや専門職に求人集中、地方は建設・介護・製造の人手不足が深刻
このように、有効求人倍率は「景気の動き」や「産業ごとの人材需要」を反映する鏡ともいえる存在です。
採用担当者が知っておくべき有効求人倍率の見方
先述した通り、有効求人倍率は景気や産業の近況を読み取るのに便利な指標となります。
ここではもう少し踏み込んで、採用担当の方が有効求人倍率を参考にする際のポイントについてお伝えしていきます。
全国平均だけでは不十分
ニュースでは全国平均の倍率が報じられますが、実際の採用活動に役立てるには 業種別・地域別 のデータを見ることが重要です。
- 製造業 → 技術職の不足が慢性的
- 介護・医療 → 常に高倍率
- 事務職 → 倍率が低く応募が集まりやすい
例:ある地域で事務職の有効求人倍率が0.5だった場合、応募が集まりやすい一方、介護職が3.0であれば「求人を出しても採用が難しい」ことが分かります。
採用コストとの関係
倍率が高い職種ほど、求人広告費や人材紹介手数料が高騰する傾向があります。つまり、有効求人倍率は 採用コストの目安 にもなるのです。
有効求人倍率を採用戦略に活かす3つのポイント
1. 採用難職種を把握して優先順位をつける
背景
有効求人倍率が高いということは「人材需要に対して供給が不足している」状態です。
特に建設業、介護、運輸、ITエンジニアなどは慢性的な人手不足にあり、求人を出しても応募が集まりにくいのが実情です。
実践の方向性
- 高倍率職種
- 短期的に即戦力採用を狙うよりも、「若手を採用して育成する」方が長期的に安定。
- 例:介護職 → 無資格者を採用し、資格取得支援制度を整える。
- 低倍率職種
- 応募者が比較的集まりやすい。採用基準を高めに設定し、スキルや即戦力性を重視できる。
- 例:一般事務 → Excelスキルや語学力などプラスアルファの要件を加える。
注意点
「倍率が低い=誰でも採れる」わけではありません。競合他社も同じ情報を見ているため、求人票や会社説明の質で差をつけることが必要です。
2. 採用手法を柔軟に変える
背景
従来の「求人広告を出す→応募を待つ」方式では、特に倍率が高い職種では成果が出にくくなっています。
実践の方向性
- 高倍率職種
- ダイレクトリクルーティング:転職サイトのスカウト機能を使い、こちらから候補者に直接アプローチ。
- リファラル採用:社員の知人・友人を紹介してもらう仕組みを整える。信頼度が高く、マッチング精度も良い。
- 地域・属性を絞った採用:地方移住者や外国人材など、新たなターゲット層を開拓する。
- 低倍率職種
- 求人媒体・転職サイト中心でも十分応募が見込める。
- ただし「大量応募の中から選ぶ体制」が必要。採用フローの効率化(Web面接・AI選考ツール導入)が効果的。
注意点
手法を変える際は「コスト」と「採用単価」を意識するようにしましょう。ダイレクトリクルーティングは時間コストが高く、リファラルは社員へのインセンティブ設計がカギとなります。
3. 求職者目線で魅力を伝える
背景
求人倍率が高い職種では、給与や待遇だけでなく「職場の魅力」をどれだけ伝えられるかが採用成功を左右します。
求職者は「同じ業務内容なら、働きやすい職場を選ぶ」傾向が強いため、情報発信力が武器になります。
実践の方向性
- 給与・待遇+αをアピール
- 成長機会 → 資格取得支援、キャリアパスの明示
- 働きやすさ → 残業時間、休暇制度、柔軟なシフト対応
- 社会的意義 → 「地域に貢献できる」「人の生活を支える」など仕事のやりがい
- 可視化の工夫
- 社員インタビュー記事や動画でリアルな声を発信
- SNSを活用して日常の雰囲気を発信(Instagramで職場の雰囲気、Xで制度や取り組みを紹介など)
- 口コミサイト対策:社員満足度を高めて外部評価にもつなげる
注意点
「盛った情報」はむしろ、入社後のギャップで早期離職につながります。
数字や事例を交え、信頼できる情報発信が重要です。
有効求人倍率の地域差
有効求人倍率を参照するにあたって、気を付けるべきポイントとして「地域」によって倍率が変動することが挙げられます。
1. なぜ都市部と地方で有効求人倍率が違うのか?
都市部の特徴(例:東京・大阪・名古屋など)
- 求職者数が多い:大学や専門学校が集中しており、新卒人材が豊富。
- 職種の偏り:事務職や営業職、サービス業の求人が多く出されるが、同時に希望者も殺到する。
- 結果:事務職などは「1つの求人に複数人が応募」するため倍率は低めになる。
地方の特徴(例:東北・九州地方の中小都市)
- 労働人口の減少:若者が都市部へ流出し、人材の供給が限られる。
- 特定産業の比重が大きい:製造業や介護職、運輸業に依存する地域では、1社あたりの求人が多くなりがち。
- 結果:求職者より求人が多く、倍率が高騰。特に介護職・建設職は地方で深刻な人手不足。
2. 地域差の具体例
- 事務職
- 東京:0.5前後(応募者が多い)
- 地方都市:0.3〜0.4(さらに低いことも)
- → 人気が集中するため「応募は来るが競争が激しい」職種。
- 介護職
- 東京:2.5〜3.0
- 地方都市:4.0〜5.0
- → 地方では「1人の求職者を複数の施設が取り合う」状態。
- 製造業(技能工・ライン作業など)
- 工場の多い地域ほど倍率が高い。特に自動車関連の集積地(愛知、九州北部)では人材不足が慢性化。
3. 採用戦略にどう活かすか?
都市部での戦略
都市部は応募者が比較的集まりやすい地域です。特に事務職やサービス業は「求人を出せば応募は来る」状況が多いです。
しかし、それは ライバル企業も同じ条件で募集している ということ。数は集まっても、自社に合った人材を採用するのは意外と難しい可能性があります。
具体的な対策
- 給与や待遇だけで勝負しない
大企業や有名企業と比べると、給与や福利厚生で中小企業が勝つのは難しいことが多いです。
→ だからこそ「働きやすさ」や「キャリアアップのチャンス」など、 お金では測れない魅力 をしっかり伝えることが重要です。 - リアルな声で差別化する
応募者は「実際に働く姿」をイメージできるかどうかで応募意欲が変わります。
社員のインタビューや日常風景をSNSや採用ページで発信することで、 「この会社なら自分に合いそう」 と感じてもらえます。
📌 例:「子育てしながら働く社員の1日の流れ」や「未経験から活躍できるまでのストーリー」を紹介すると効果的です。
地方での戦略
地方は都市部と違い、そもそも応募者の数自体が少ないのが大きな課題です。
特に介護職・製造業・運輸業などは どの会社も人を欲しがっているため取り合い状態 になりやすく、求人広告を出すだけでは応募が集まりにくいのが現実です。
具体的な対策
- ダイレクトリクルーティングやリファラル採用を活用
求人広告で待つのではなく、企業側から動いてアプローチする必要があります。
- ダイレクトリクルーティング:求職者データベースやSNSを使って直接スカウトする
- リファラル採用:社員の紹介で新しい人材を呼び込む(紹介制度に報酬をつけると効果大) - Uターン・Iターン人材をターゲットにする
「地元に戻って働きたい」「都会を離れて地方で暮らしたい」という層に積極的に情報を届けましょう。
住宅補助や地域の暮らしやすさを発信すると、移住を考えている人の心に刺さります。 - 外国人材の採用を検討する
特に介護や製造の現場では、外国人スタッフが大きな戦力になっています。
制度も整備されつつあり、語学研修や受け入れ体制を用意することで、安定した採用が可能になります。
📌 例:「地元に戻ってきた30代社員が、製造業でリーダーに成長した」というストーリーを紹介すれば、Uターン希望者の共感を得やすいです。
採用担当者がよく陥る失敗
- 全国平均の倍率だけを見て判断してしまう
⇒実際は職種や地域によって有効求人倍率は変化します。自社の求人内容によって対応する有効求人倍率を確認するようにしましょう。
- 倍率が高い職種でも「求人票だけで十分」と考える
⇒最近では「求人を出せば人が集まる」ことはありません。自社の魅力を発信し求職者に選んでもらう必要があります。
また、ダイレクトリクルーティングなど企業側から求職者へアプローチする手段を活用することも選択肢として考えられます。
- 採用が難しい理由を「人がいないから」と片づけてしまう
⇒本当の理由が別にあるのではないか考える必要があります。
例えば、他社と比べて自社の魅力が外部に伝わっていないことや差別化ができていないことなどが考えられます。
こうした失敗を避けるためには、倍率データを 「採用戦略の材料」として活用する姿勢 が大切です。
5. まとめ
有効求人倍率は労働市場の需給バランスを読み取るうえで非常に重要な指標となります。
採用活動を行う際は大いに役立つ指標ですが、いくつか注意すべきポイントがあります。
- 地域別の倍率データを把握する
「全国で〇倍」ではなく、「自社のある地域・職種では何倍か」を確認する。 - 職種ごとに採用難易度を判断する
倍率が高い職種は育成採用やリファラル採用を強化、低い職種は応募の質を重視する。 - 戦略を地域・職種ごとにカスタマイズする
都市部では「差別化の情報発信」、地方では「能動的なアプローチ」が有効。
以上、これら3点については採用担当者の方は注視するようにしましょう。
有効求人倍率から得られる情報を正確に読み解き、実際の採用活動に生かすことができれば効果的かつ効率的な採用活動に一歩近づくことができるのではないでしょうか。
採用でお困りの企業様へ
採用活動を任されたけど何から始めていいかわからない…
とお悩みの採用担当者の方も多いかと思います。
弊社は40年以上人材業界で企業様の採用活動のサポートをしてまいりました。
その中で、「単なる採用支援ではなく、本質的な問題の解決のために伴走する」ことをモットーに様々なご相談をいただきます。
どんな些細な下でも結構です。「応募者が集まらない」「求人を出しても決まらない」などのお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。