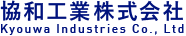外国人採用の現状と今後の見通し ~日本企業が知っておくべき最新動向~
はじめに
日本の労働市場では少子高齢化が進行し、深刻な人手不足が続いています。
その中で、外国人採用は今や採用戦略の柱のひとつです。
本記事では、最新データと政府方針をもとに、現状の実態と今後の日本における外国人採用の見通しを整理します。
1. 現在の外国人労働者の状況
2024年10月末時点で、日本国内で働く外国人労働者数は約 230万人 に達し、過去最高を記録しました。前年からの増加は12.4%に及び、特に注目すべきなのは高度外国人材(「専門的・技術的分野」の在留資格)が 約72万人(前年比+20.6%) と大きく伸びている点です。
国籍別では、ベトナムが約57万人で最多、次いで中国(約41万人)、フィリピン(約24万人)が続き、東南アジア出身者が多いのも特徴です。
2023年末段階では、全就業者(約6,781万人)のうち「29人に1人」が外国人という割合で、身近な存在になりつつあります。
2. 地域・業種別の動向
業種別では、 医療・福祉分野の外国人労働者が前年比28.1%増 と著しい伸びを見せており、高齢化により介護人材の需要増加も相まって、今後も需要が続く見込みです。
また建設や製造業においても、技能実習生や特定技能制度のもとで外国人労働者の存在が大きくなっており、施工管理や電気通信などの業務では即戦力への期待も高まっています。
東京都や大阪など都市部に集中しがちだった採用に対し、地方企業でも積極的に外国人採用を検討・実施するケースが増えています。
3. 政府の制度整備と今後の方向性
政府は外国人労働者受け入れのための制度整備を進めており、特定技能制度の拡充が注目されます。2024年度からの5年間で、特定技能制度での外国人受け入れ上限を 82万人 に設定し、従来の対象業種に「運送」「鉄道」「林業」「木材産業」などが追加されました。これは前計画の2.4倍の規模であり、制度拡大の流れが加速しています。
また、技能実習制度に変わる新たな制度として、研修目的だけでなく スキル習得と定着を重視した在留制度 の導入が進められています。一定期間働いた後に転職や永住申請の可能な仕組みを作ることで、外国人労働者の権利保護と定着が期待されます。
ただし、直近では外国人受入数の上限設定や社会統合の問題を巡る議論も活発化しており、2025年8月には政府が 外国人住民数の上限引き上げの是非 を含めた政策見直しが推奨された報告も示されました。
4. 将来的な人材需要の見通し
JICA(国際協力機構)による予測では、2040年には外国人労働力が 約591万人 必要とされる一方、現状のペースでは 約100万人不足 するとの推計があります。
このギャップを埋めなければ、政府の経済成長目標(年1.24%)の維持も困難とされます。
これを踏まえ、今後は単なる量の確保だけでなく、高度・専門性を備えた外国人人材 の採用戦略、さらには多様性の受け入れ体制の整備が重要になってきます。
5. 企業が取るべき対策と戦略
現行の採用環境と将来の見通しを踏まえ、日本企業が実践すべきポイントは以下の通りです。
(1) 受入インフラの整備
語学・生活支援、社内研修の整備により、外国人の早期戦力化と定着を支える体制づくりが重要です。
(2) 制度を戦略的に活用
特定技能や高度外国人人材向けビザなどを適切に活用し、自社の採用ニーズに応じた制度選定が求められます。
(3) ブランディングと広報強化
多文化共生・企業の国際化を前面に出し、採用ブランディングを行うことで応募喚起につながります。
(4) 中長期的な視点での採用計画
即戦力だけでなく、自社に長く貢献できる人材とのミスマッチを防ぐ視点も欠かせません。政府制度による制度変更の余地もあるため、柔軟な採用体制が求められます。
まとめ
- 外国人労働者数は過去最高(約230万人)を記録。高度人材の増加が顕著に。
- 医療・福祉、建設、IT業界などで特に需要が伸びている。
- 政府は制度の拡充と定着支援の方向へ舵を切っている。
- 2040年には約100万人の外国人労働力が不足すると予測され、今後ますますの受け入れ強化が必要。
- 企業としては受入体制整備、制度活用、採用ブランディング、長期戦略が鍵となります。
出典一覧
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況(令和6年10月末現在)」をもとにした解説
- 労働市場における外国人比率
- 業種別動向(医療・福祉分野など)
- 制度改革・政府方針
- 将来予測(JICA試算)
- 企業が取るべき対応