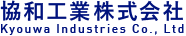採用担当者必見!派遣と紹介をどう使い分ける?費用・スピード・定着率の違いを解説
派遣と紹介の違い、最適な使い分け方【完全ガイド】
人材不足が慢性化する今、多くの中小企業やスタートアップでは「派遣と人材紹介、どちらを使うべきか?」という悩みを抱えています。両者は似ているように見えて、仕組み・費用・リスク・成果の出方が大きく異なります。この記事では、人材サービスの専門知識と実際の事例をもとに、派遣と紹介の違いを徹底的に解説し、最適な使い分け方をご紹介します。
派遣と紹介の基本的な違い
派遣とは
- 雇用関係:派遣スタッフは派遣会社に雇用され、派遣先企業に派遣される
- 契約期間:数日~最長3年までの契約が一般的
- 費用形態:時給単価 × 稼働時間(+派遣会社のマージン)
- 特徴:急な欠員補充や短期業務に強い
紹介とは
- 雇用関係:求職者と採用企業が直接雇用契約を結ぶ
- 契約期間:正社員・契約社員採用が中心
- 費用形態:入社時に紹介料(年収の20〜35%が相場)を支払う
- 特徴:中長期の人材確保に強い
よくある誤解と注意点
- 「派遣=安い」わけではない
実際には、派遣会社のマージンが加わるため、時給換算すると直接雇用より高くなるケースが多いです。 - 「紹介=必ず定着する」わけではない
年収に対して高額な紹介料を払っても、早期離職のリスクはゼロではありません。再保証制度の有無を確認する必要があります。 - 「紹介の方が即戦力」も誤解
条件が厳しい職種では、採用までに数カ月かかることもあります。
派遣と紹介の費用比較(例)
- 派遣社員(事務職)
時給2,000円 × 160時間 × 12カ月 ≒ 年間約384万円 - 人材紹介(年収350万円で採用、紹介料30%)
紹介料 ≒ 105万円(初年度のみ)
→ 短期では派遣の方が便利ですが、1年以上雇用を見込むなら紹介の方がコスト効率が良いケースも多いです。
法律面での違い(派遣法と職安法)
- 派遣法
派遣期間の上限(原則3年)、派遣先責任者の選任、派遣料金と賃金のバランス規制など、細かいルールが定められています。 - 職業安定法
紹介手数料の上限、個人情報の適正管理、虚偽求人の禁止などが定められています。
法律面を理解せずに利用すると、コンプライアンス違反のリスクがあるため要注意です。
導入ステップ:派遣と紹介の選び方
- ニーズの明確化
「短期の欠員補充なのか」「中長期的な人材確保なのか」を整理する - 費用シミュレーション
派遣なら年間コスト、紹介なら採用時コストを試算 - リスク管理
早期離職保証や派遣社員の交代対応ルールを確認 - 現場の受け入れ体制
OJTや教育コストも含めて考える
事例:ある中小製造業のケース
- 背景:繁忙期に人手不足が発生
- 対応:短期的には派遣社員を活用し、生産ラインの欠員をカバー
- 長期戦略:同時に人材紹介を活用し、経験者を正社員として採用
- 結果:短期と長期のバランスを取り、採用コストを最適化
派遣と紹介を組み合わせる戦略
- 派遣で短期的な穴埋め+紹介で長期的な人材確保
- 派遣社員から直接雇用への切り替え(紹介予定派遣)
- 繁忙期は派遣、平常時は紹介採用で安定人材を育成
まとめ:最適な使い分けのポイント
- 短期・即戦力なら派遣、長期・定着狙いなら紹介
- 費用だけでなく、教育コストや離職リスクも加味する
- 派遣と紹介を「併用」する戦略がもっとも現実的
採用市場が激化する中で、単一の手法に頼るのではなく、派遣と紹介を組み合わせた柔軟な戦略が求められます。
採用でお困りの企業様へ
私たち協和工業株式会社では、派遣・紹介の両サービスを提供し、企業の採用課題に合わせた最適な人材活用をご提案しています。
「短期的にすぐ人が欲しい」「定着率を高めたい」といったお悩みに、経験豊富な担当者が伴走支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。